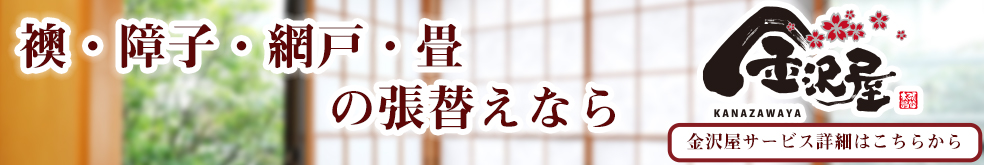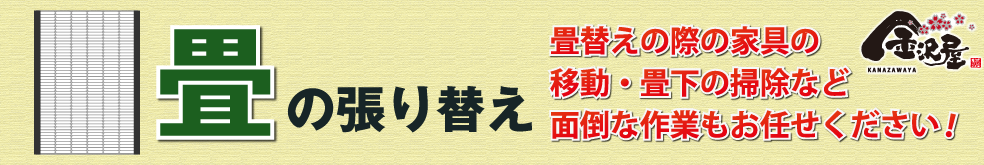目次
畳の3つの部位と寿命
畳の寿命は、畳表(たたみおもて)・畳床(たたみどこ)・畳縁(たたみべり)で違います。それぞれの部位ごとに、特徴と寿命をみていきましょう。
畳表
畳表とは、畳表面の天然のい草が織られたゴザ部分です。最近では国産だけでなく、安価な外国産のい草も使われています。ただし、外国産は国産のい草と比べて、一般的には耐久性や弾力性などの品質が低いとされています。国産畳表の中にも品質に差があり、グレードが分けられています。
また、い草ではなく和紙や樹脂を原料とした化学製品を繊維状にして、い草と同じように織って畳表にしている化学表もあります。化学表は、変色がしづらく防カビなどにも優れているという特徴があります。
畳表の交換時期は6年〜10年が目安です。品質により寿命に差があり、高品質のい草であればあるほど長持ちする傾向があります。
寿命は、部屋の日当たりや使い方によっても変わってきます。交換時期は、畳表の色や風合いの変化で判断しましょう。
畳は使っているうちに、日当たりによるい草の変色やシミなどの汚れが生じます。光沢がなくなってきたり、目立つようなささくれが増えてきたりして風合いが悪くなった場合も、寿命と考えましょう。
畳床
畳床は、畳の土台となる芯の部分です。伝統的に、稲ワラを重ねて麻ひもで締め付けて作られてきました。近年では、稲ワラと発泡プラスチックであるポリスチレンフォームを組み合わせた畳床や、ポリスチレンフォームと木材を圧縮したインシュレーションボードからできているものもあります。
ワラを使用した畳床は、湿気を吸い取ってくれる吸湿機能があります。また耐久性にも優れているので、メンテナンス次第で長持ちします。
ワラをまったく使っていない畳床には、ダニなどが発生しない、断熱効果に優れているという利点があります。
畳床の寿命は、一般的に10年〜20年程度といわれており、交換時期は踏み心地で判断できます。踏んだときに、フワフワしていたりへこんだりしたら寿命と考えましょう。ただし、丁寧なメンテナンスを定期的に行えば、40年〜50年使えることもあります。
畳縁
畳縁は畳の側面に付いている生地の部分です。畳は長方形の形状をしていますが、長い方の部分(側面)に畳を囲うような具合で縫いつけられています。短い方の部分には畳縁は通常付いていません。
畳縁の主な役割は、畳表を補強することです。また、畳と畳の隙間を埋めるのも、畳縁の重要な役割です。もし畳縁がなかったとすれば、隙間が生じやすくなってしまいます。畳縁の色や模様は種類が豊富にあるため、装飾としての役割も果たしています。
畳表と同様に畳縁も経年劣化すると、少しずつ変色していきます。畳表が寿命を迎えるくらいだと、畳縁も寿命というケースが多いです。
畳の寿命を判断するには
畳の寿命は使用年数である程度は判断できますが、使用環境なども関係してきます。使用年数だけでなく以下のような要素も参考にしつつ、畳の寿命を判断しましょう。
畳表の色

新しい畳と古くなった畳では畳表の色が異なります。畳の編み方やい草の種類によってもやや風合いが異なりますが、新しい畳ならほぼ緑色といって良いでしょう。年月を経て古くなってくると、次第に黄色っぽくなったり、黒ずんで茶色っぽくなったりします。
このような色合いの変化がみられたら、交換のサインと捉えましょう。
また、直射日光を長く浴び続けた場合にも、日焼けにより変色していきます。部分的に変色していたり、黒い筋が目立つようになっていたりする場合も、交換のタイミングです。
畳表の状態
あまり年数が経っていなくても、新しかった頃と比べて光沢がなくなっていると感じることもあるでしょう。そのくらいの劣化であれば、使い続けたいと考える方も多いかもしれません。
しかし、光沢がなくなったのに加えて、汚れ・シミ・ささくれ・切り傷などが目立つようであれば、交換時期の目安になります。
そのまま使い続けることもできますが、見栄えがあまりよくありません。ささくれや切り傷ができている部分が広がってしまうこともあります。
また、見栄えの良し悪しだけにとどまりません。ダニなどの害虫が湧く原因になったり、ささくれが皮膚に刺さったりすることもあります。健康と安全のためにも、畳表の状態が悪くなったら交換するのがおすすめです。
特にダニが発生している場合には、放置してしまうと、同じ部屋のほかの畳にも影響が及ぶおそれがあります。
お手入れの状況

畳の寿命は普段のお手入れの状況にも左右されます。普段からきちんと掃除や換気をしていれば、目安とされている年数よりも長持ちするケースが大半です。
しかし、掃除の頻度が低く、換気もあまりしていない場合には、長持ちはあまり見込めません。カビやダニが発生しやすくなるため、畳の寿命も通常より短いと捉えておきましょう。
また、布団やカーペットを敷いたままにしている場合や重い家具を置いている場合にも、通気性が悪くなり、畳の状態が悪化しがちです。
畳床の感触
畳の上を歩いたときの感触も寿命を判断する上で重要です。ふわふわする感触があったり、ぐにゃりとへこむような違和感があったりするなら、替え時は近づいています。
また、このような違和感がある場合には、畳床の藁に原因があるケースが大半です。そのまま放置しておいても、自然に改善することはありません。メンテナンスで元の感触に戻すのも困難です。
畳の寿命を延ばすには
畳は普段の使い方によって寿命を延ばすことができます。ここからは、気をつけたい4つのポイントを紹介します。
湿気に気を付ける
畳は水分を吸収しやすい素材でできています。湿度に合わせて空気中の水分を吸収・排出する働きがあり、室内の湿度を調整しています。しかし湿度が高い状態が続くと、ダニやカビが発生しやすくなるので要注意です。
ダニやカビの発生を防ぐためには、定期的に換気をするなどして、室内の通気性を良くすることが大切です。また、畳の上にカーペットや布団を敷きっぱなしにしていると、湿気がこもりダニやカビの原因となります。
畳の中には、湿気に強い材料を使っているものもあります。部屋の湿度が気になるのであれば、そういった機能性畳も検討してみましょう。
傷を付けないようにする
畳表のい草はささくれになりやすいので、傷を付けないようにしましょう。畳は雑に扱わないことが大切です。
具体的には、家具を移動するときに、引きずらないようにしましょう。また掃除機をかけたり雑巾掛けをしたりする際も、い草に負担がかからないよう畳の目に沿って掃除をします。
掃除をこまめにする
ダニやカビの発生原因は、湿気だけではありません。汚れがあるとダニやカビが発生しやすくなるので、こまめな掃除で清潔な状態を保ちましょう。こぼしたジュースなども吸収してシミが残りやすいので、すぐに拭き取るようにします。
掃除方法としては、畳の目に沿ってゆっくりと掃除機をかけます。掃除機で吸い取れない畳の隙間に挟まった小さなゴミやホコリは、ほうきで掻き出すと良いでしょう。
皮脂などを畳表に吸着した汚れを取りたい場合は、雑巾で乾拭きします。畳は水分を吸収しやすいので、できるだけ水拭きは避けるようにしましょう。
また、日陰干しをすることも、畳を長持ちさせるために良い方法です。ただし直射日光が当たると変色してしまうので、必ず日の当たらない風通しの良い場所で干すようにしましょう。
畳干しする
畳干しとは、和室に敷かれている畳を天日干しすることです。畳に含まれている湿気を飛ばせるため、ダニやカビが発生しにくくなります。
できれば、毎年春と秋に1回ずつ、年に2回の頻度で畳干しをするのがおすすめです。湿度が低い晴れた日に行いましょう。屋外に干すのが望ましいですが、スペースの都合などで難しい場合には、室内でもある程度は効果が見込めます。
ただ、畳干しをするためには、畳を取り外さなければなりません。これまで畳を持ち上げたり外したりしたことがない方も多いかもしれませんが、マイナスドライバーを使用すれば、取り外しは可能です。
畳の外し方や畳干しについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
「畳を天日干しする効果とは?畳を長持ちさせるお手入れ方法を紹介」
畳のメンテナンスの方法
長持ちするように畳を使っていても、どうしても経年劣化は生じます。気持ち良く畳を使用するために、古くなってきた畳はメンテナンスを行いましょう。畳のメンテナンス法としては、「裏返し」「表替え」「新調」の3種類があります。
裏返し
裏返しとは、それまで使っていた畳を再利用して張り替える方法です。畳表は両面を使用できるので、一度畳床から剥がし使っていなかった面を上にして張り替えます。畳表も畳床も寿命までいっていない畳に有効な方法です。
キレイな面が上にくるので新品のような色合いが戻ります。ただし、裏返しはあくまで畳表が再利用できる場合のみに使える方法です。使い始めてから数年経つと、畳表の奥の方まで日焼けで変色してきますし、損傷も激しくなります。
奥の方まで畳が傷んでいる場合は、ほかのメンテナンス方法を実施しましょう。
表替え
表替えとは、畳表のみを新品にして、畳床はこれまで使っていたものを再利用する方法です。表面のい草部分が新しくなるので、見た目だけでなく畳特有の香りやい草のもつ吸湿作用なども回復します。
裏返しをしたことのある畳や、一度も裏返しはしていないけれど畳表の奥まで日焼けや損傷している場合に用いる方法です。
ただし畳床は変わらないので、踏み心地は変わりません。畳床がへたっていて踏んだときにフワフワしたりへこんだりする場合は、畳床も新しくする、新調がおすすめです。
新調
畳を丸ごと新品にする方法を新調といいます。畳床、畳表、装飾と保護のために畳の長辺についている畳縁(たたみべり)、すべて新しくなります。
畳床まで劣化が進み、裏返しも表替えもできない状態のときに行う方法です。畳を踏んだときに沈んだり、ダニやカビが発生したりしてきたら、畳床の交換時期で新調が必要と考えましょう。
完全に新しい畳にするので、畳床や畳表の素材や色を一から選べます。汚れや湿気に強い畳などに機能性のある素材を使いたいときは、畳床が古くなくても新調しましょう。
ご使用の畳が寿命になってきたと感じたなら、メンテナンスの時期です。畳や襖などの張り替え専門店である金沢屋は、専門の知識と技術で必要なメンテナンスを行います。
ご連絡をいただけましたら無料で現地に赴き、畳の状態を見極めて必要なメンテナンス方法をご提示します。見本帳をお持ちしますので、お好みの畳をその場で選んでいただくことが可能です。
畳の色が黄色くなってきたりい草のささくれを感じたりするようになったなら、ぜひお気軽に金沢屋にご相談ください。
まとめ
畳の寿命は、畳表と畳床で異なります。普段の使い方によって、寿命の長さは大きく変わってくるので、湿気や汚れ、傷には十分注意しましょう。畳のメンテナンス法は3つあり、畳表と畳床の状態によって利用できる方法は異なります。専門業者に確認してもらい、適切なメンテナンス方法を選びましょう。