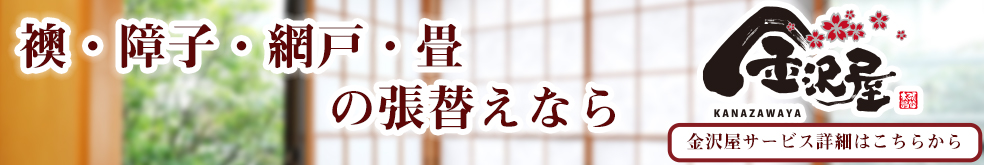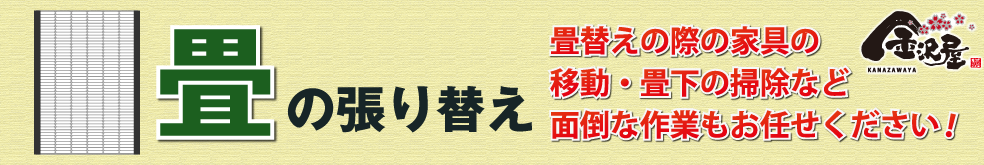畳掃除の基本を知ろう!

畳は傷みやすくデリケートな素材であるため、掃除をする際はゆっくり丁寧に行うことが重要です。ここでは、畳を美しく、清潔に保つための基本的なポイントを確認していきましょう。
畳の目に沿って掃除する
畳の掃除において最も基本的なのは、畳の繊維の向き、つまり「畳の目」に沿って掃除を行うことです。畳の目とは、畳の表面の繊維が一定の方向に並んでいることを指し、この目に沿って掃除をすることで、畳を傷めることなく効率的に汚れを取り除くことができます。
反対に、畳の目に逆らって掃除をすると、畳を傷つける原因となります。掃除機を使用する場合も、ほうきで掃く場合も、畳の目に沿ってゆっくりと動かすことが大切です。畳の目に沿って掃除することで、畳の美しさをキープしながら、清潔な状態を保つことができます。
1畳当たり約1分かけて掃除する
畳の掃除は、急いで行うよりも、1畳当たり約1分の時間をかけて丁寧に行うことが推奨されます。これは、畳の目に入り込んだ細かなゴミやホコリをしっかりと取り除くためです。急いで掃除をすると見落としがちな汚れも、時間をかけて丁寧に掃除することで効果的に除去できます。
仕上げに乾拭きする
畳掃除の最終工程として、乾拭きをすることが重要です。畳は水分を吸収しやすく、湿気が多い状態が続くとカビの発生原因となります。そのため、掃除の仕上げには必ず乾いたタオルや雑巾を使用して、余分な水分を取り除いてあげることが大切です。
乾拭きをすることで、畳が清潔で健康的な状態を保つことができ、長期間にわたって畳の美しさを維持することが可能になります。
基本的な畳の掃除方法

掃除機で掃除する場合と、ほうきで掃除する場合をそれぞれ説明します。
掃除機を使う場合
まず、掃除機を使用する畳の掃除の手順は以下のとおりです。
1.畳の目に沿って、掃除機をかける
2.乾拭きをする
3.集めたゴミを掃除機か塵取りで回収する
また、掃除機を使用する際は、畳専用の低い吸引力設定や、畳モードがある場合はそれを利用しましょう。そのとき、畳の目に沿って掃除機をゆっくり動かすことがポイントです。
その後、取り切れなかったホコリやゴミを取り除くように乾いた雑巾で乾拭きを行い、集めたゴミを回収します。
ほうきを使う場合
次に、ほうきを使用する畳の掃除方法を説明します。手順は以下のとおりです。
1.畳の目に沿って、ほうきを掃く
2.乾拭きをする
3.集めたゴミを掃除機か塵取りで回収する
ほうきを使用する場合も、畳の目に沿って掃くことが大事です。ほうきで掃くことにより、掃除機では取り除けない細かいホコリやゴミをかき出すことができます。
掃除機と同様、畳掃除の仕上げには乾いた布で乾拭きをします。その際も、畳の目に沿って拭きましょう。
畳の掃除では水拭きは基本的に避けるべきですが、どうしても汚れがひどい場合は、少量の水を使って部分的に拭き取っていきます。水拭き後はしっかりと乾拭きをして水分を残さないようにしましょう。
また、掃除でよく使われる重曹やセスキ炭酸ソーダなどは畳掃除に使用しないよう注意してください。畳を傷めたり、変色させたりする原因になるため、汚れがひどいときには、水拭きと乾拭きのみでするのがポイントです。
【ケース別】畳の掃除方法

ここまでは、基本の畳掃除について紹介しました。
では、畳が汚れていたりカビが生えたりしている場合は、どのように掃除すれば良いのでしょうか。ここからは、畳の状態に応じた掃除方法について紹介します。
汚れが気になる場合
畳のある生活をしていると、「キレイに使っているつもりなのに、いつの間にか汚れが付いてしまっていた」という経験も多いのではないでしょうか。畳は汚れが落ちにくいので、付いてしまった汚れは早めに取り除くのが鉄則です。
少しの汚れであれば、ほこりを取り除き、そのあとに水拭きと乾拭きをすることで落ちる場合があります。とはいえ、前述したように水分は傷みの原因になるため、畳に水気を残さないよう雑巾は固く絞ってから使用しましょう。
上記の方法では落ちない強い汚れの場合、クエン酸を使うのがおすすめです。クエン酸を使って掃除すると、汚れが落ちるだけではなく、カビやダニの予防にもなります。
クエン酸を使った畳掃除の手順を以下に紹介します。
■用意するもの
雑巾(2枚)、バケツ、水、クエン酸、ゴム手袋
■クエン酸を使った汚れ落としの準備
1. 水(お湯)をバケツ半分くらいにまで入れる
2. バケツに小さじ1のクエン酸を入れる
3. 雑巾を浸して固く絞る
4. 絞った雑巾で畳の水拭きを行ったあと、もう1枚の雑巾で乾拭きをし畳を乾燥させる
水よりも乾燥するのが早いので、可能であればお湯を使って掃除をしましょう。また、クエン酸を使用する際は、肌荒れ防止のためにもゴム手袋を使うことをおすすめします。
クエン酸水を使った畳の水拭きについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。
カビが発生した場合
梅雨から夏にかけては、カビが生えやすい時期です。そのため、この時期になると、いつの間にか畳にカビが生えてしまっていることがあります。
畳に使われている天然素材のい草は、湿気を吸収する性質があるため、畳の上に布団やカーペットやラグを敷いている家庭は、カビが生えやすくなってしまうのです。
畳にカビが生えてしまったときは、「早く取り除きたい!」と慌てて水拭きをするのではなく、消毒用エタノールを使用するのがおすすめです。
消毒用エタノールをカビの生えた場所にスプレーし、乾いた雑巾やタオルで乾拭きしましょう。このとき畳に湿気が残ってしまうと、さらにカビが生える原因となりますので、湿気を残さないよう丁寧に乾拭きをしてください。
拭き取ったあとは、エアコンの除湿機能や扇風機を使うか、部屋の窓を開けて風通しを良くして畳をしっかり乾燥させましょう。
カビが生えた畳の正しい掃除法については、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。
ダニが繁殖した場合
前述したように、畳は湿気を吸収する性質があるため、湿気を好むダニも繁殖しやすいです。
逆にいえば、ダニは乾燥に非常に弱い生き物であるため、ダニが繁殖した畳は天日干しにするのが有効です。
まずは、畳の表面にいるダニを掃除して取り除きましょう。掃除機などで可能な限り取り除いたあとに畳を取り外し、裏側も掃除して駆除することが大切です。ダニは裏側まで入り込んでしまっているため、見逃さずに取り除きましょう。
畳からダニやほこりなどを取り除いたら、日当たりと風通しの良い場所で乾燥させるのがおすすめです。もしも天日干しの場所を確保するのが難しければ、市販の燻煙剤でダニを取りましょう。
天日干しをやり過ぎると、畳が日焼けして変色したり傷んだりする場合があるため、半年~1年に1回ぐらいの頻度で行うのがベストです。湿度が低く、乾燥してよく晴れた日に天日干しをしましょう。ただし、畳床(たたみどこ)の種類によって畳の重さが違うため、天日干しする場合には注意してください。
畳のダニを除去する方法については、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。
「畳のダニを駆除する4つの方法と繁殖させないためのポイント」
畳が日焼けした場合

畳は、紫外線による経年劣化で茶色く日焼けしてしまいます。日焼けを元に戻すには、クエン酸もしくはお酢を使うのがおすすめです。クエン酸やお酢は酸性の性質を持ち、畳の変色を 薄くする効果があります。
まずは、掃除機やほうきで畳の上のほこりを取り除きます。掃除の手間がかかってしまうので、しっかり取り除くことが大切です。
ほこりを取り除いたら、ぬるま湯で10倍に薄めたクエン酸もしくはお酢で水拭きします。畳は水分に弱いので、なるべく水分を絞ってから拭きましょう。拭いた後は、乾拭きで水気を取ればお掃除は完了です。これで畳の日焼けが戻っているか確認しましょう。
飲み物や調味料をこぼした場合
飲み物や調味料などをこぼした場合は、塩を使うのがおすすめです。塩は臭いやぬめりを取る効果、研磨作用、抗菌作用が期待できます。
飲み物や調味料はシミが残るため、こぼした液体はすぐに拭き取ることが大切です。汚れに塩を振り、その塩が湿るまで放置しましょう。塩が湿ってきたら、歯ブラシまたはスポンジで汚れをかき出すように優しくこすり、掃除機で塩を取り除きます。
固く絞った雑巾で拭き取り、さらに乾いた雑巾で乾拭きすれば完了です。飲み物や調味料が、畳の中に完全に染み込む前に素早く行いましょう。特にお子さまがいる家庭や、畳の間で食事をするご家庭は覚えておくと便利です。
畳の凹みが気になる場合
畳の上に重い家具などを載せると、凹みが気になることもあります。家具の移動などをした際に凹みが気になる場合は、アイロンを使って直しましょう。
まずは凹んだ部分に固く絞った雑巾を当てます。雑巾の上からアイロンをかけて、最後に乾いた雑巾で乾拭きするだけで凹みの補修は完了です。深い凹みの場合は、何度か繰り返せば凹みが目立たなくなります。
畳は水分に弱いので、最後の乾拭きだけは忘れないようにしましょう。しっかりと畳を乾かすことが大切です。
畳掃除で避けるべきこと

畳は、お手入れひとつで長持ちするか傷みやすくなるかが大きく変わります。
ここからは、掃除のときに必要以上に傷めないよう、畳の掃除で避けるべきことについて紹介します。
避けるべきこと1|水拭きをする
前述したとおり、畳は水分に弱く、水分を吸うとカビが発生しやすい素材です。そのため、基本的に畳の掃除は乾拭きをするのが鉄則となっています。
どうしても水で濡らした雑巾で拭きたいような、気になる汚れがある場合は、固く絞った雑巾で水拭きしてみましょう。水拭きのあとは、必ず乾拭きをして畳を乾燥させることが大切です。畳の乾燥を怠るとカビやシミの原因になるので注意しましょう。
避けるべきこと2|ロボット掃除機を使う
ロボット掃除機は、畳の目を感知して動いているわけではありません。動きはランダムで、畳の目に沿ってくれないのが一般的です。そのランダムな動きは、畳を傷めてしまう原因となります。
また、畳のささくれが出ている箇所は、ロボット掃除機がゴミと誤認識するおそれもあります。そのまま使用していると畳表(たたみおもて)をダメにしてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
ロボット掃除機は、非常に便利なツールですが、畳には適していないので使わないようにしましょう。
避けるべきこと3|重曹やセスキ炭酸ソーダを使う
掃除に使う薬品といえば、近年では重曹やセスキ炭酸ソーダが人気です。これらは、フローリングやキッチンなどの水回りにはすさまじい威力を発揮しますが、畳には適していません。
どちらもアルカリ性なので、い草畳に使用すると黄色く変色してしまいます。また、畳の中に成分が残ると、それが化学変化を起こして黒い汚れになってしまいます。
畳の汚れ落としには重曹やセスキ炭酸ソーダではなく、やはりクエン酸を使うのが良いでしょう。
避けるべきこと4|カビ取り剤や漂白剤を使う
畳にカビが発生したときなどは、カビ取り剤や漂白剤を使用する人もいるかもしれません。しかしこれらは、薬剤の効力が強いため、畳が変色してしまうおそれがあります。
カビの除去には、アルコール消毒液と水拭き、乾拭きで対処しましょう。
避けるべきこと5|粘着クリーナーを使う
前述しましたが、畳に粘着クリーナーを使うのはおすすめできません。強い粘着力で、毛羽立ちやほつれを起こしてしまい、畳を傷つけてしまうおそれがあります。
粘着クリーナーはカーペット掃除においては必須ともいえるツールですが、畳には適していないので使わないようにしましょう。
このように、畳掃除ではいくつか避けておくべきポイントがあります。
「自分で掃除すると畳を傷めてしまうかも…」と不安なようであれば、プロに任せるのもおすすめです。
和室に関するプロをお探しなら、金沢屋にご相談ください。スタッフが、畳を傷めることなくキレイに掃除を行います。もちろん掃除だけでなく、張り替えや新調など、畳のことならなんでも対応可能です。
金沢屋は全国350か所に店舗がございます。まずは、メールや電話などで汚れの状態についてお聞かせください。
畳を美しく保つコツ3つ

畳はデリケートな素材なのでこまめにお手入れすることが大切です。ここでは、畳を美しく保つコツを3つ紹介します。
こまめに掃除する
毎日もしくは2日に1日程度、ほうきや掃除機で簡単に掃除をすると畳が長持ちします。拭き掃除をするときには、畳の目に沿って行うのがポイントです。掃除機をかけるときも同様に、畳の目に沿って掃除機を動かしましょう。
掃除機をかける場合は、1畳につき40~60秒かけるとゴミがとれます。ダニの発生を防ぐにはホコリやゴミを溜めないことが鉄則なので、毎日の掃除が大切です。毎日畳を見ることでシミや汚れにすぐ気づいて対処でき、畳を美しく保つことができます。
天日干しをする
ダニやカビの発生を防止するには、畳を乾燥させることも必要です。天気が良い日に日当たりの良い場所に干して、湿気をとりましょう。
ただし、天日干しをする頻度が高いと、日焼けして変色したり劣化の原因になったりするため注意が必要です。理想は、半年~1年に一度くらいの頻度です。湿気の多い地域は3ヶ月~半年の頻度で行うと良いでしょう。
重いものを置かない
畳の上にベッドやタンスなど大きな家具を置くと、変形や変色の原因になります。また、動かしづらい物を置くことで掃除しづらくなるというデメリットもあるのです。
畳を長持ちさせるには、なるべく畳の上に何も置かないようにしましょう。どうしても重いものを置かなければならないときは、定期的に部屋の模様替えを行い、同じ場所に置き続けない工夫をすることも必要です。
まとめ
畳は調湿機能や心地よい香りで、長年にわたり日本の家庭に愛されてきた伝統的な床材です。しかし、素材は傷つきやすくデリケートであることから、掃除しにくい点もあります。畳を掃除する際は、畳の目に沿って丁寧に掃除することを心がけましょう。
畳の掃除をしても汚れやカビが取れない、変色してしまったなどの場合は、畳の張り替え・新調を検討するのもひとつの手です。
襖や障子、網戸、畳の張り替え専門店である「金沢屋」なら、予算や希望に応じて最適な畳を提案いたします。全国約350店舗展開しているため、気になる方はぜひお問い合わせください。