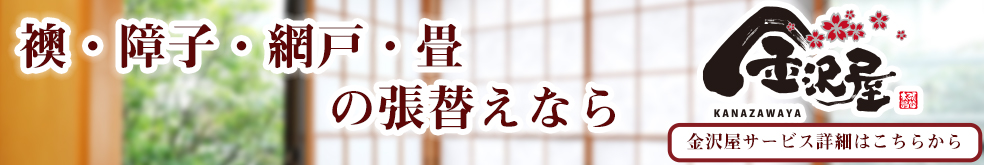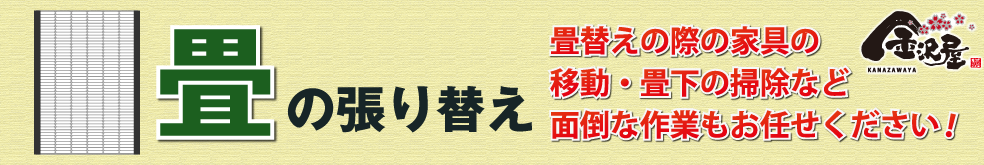畳の傷やへこみ、汚れを放置しておくとどうなる?

畳を使っていると、傷やへこみ、汚れが生じる可能性があります。放置しておくとアレルギーの原因になったり、傷みがひどくなったりして畳が長持ちしにくくなってしまうのです。
ここでは、畳のメンテナンスを怠るとどうなるのかを紹介します。
ダニやホコリアレルギーの原因になる
畳の汚れを放置すると、アレルギーの原因になるおそれがあります。畳に染み付いた汗や汚れを餌とする害虫が、外から侵入して畳に棲みつくこともあるのです。そうなると、畳が不衛生な状態になってしまい、ダニやホコリアレルギーの原因になります。
アトピー性皮膚炎の症状がある人や、アレルギー体質の人は、こうした環境で住み続けると悪化する可能性も高まります。畳の汚れやホコリはこまめに掃除しましょう。
カビの原因になる
畳にとって、水分は最大の敵でもあります。梅雨の湿気の時期や、風通しが良くない場所にあるだけでカビが生えやすいのが特徴です。そのため、液体をこぼしたり、湿気の多い状態で畳を使用し続けたりすると、カビが生える可能性が増します。
畳がある部屋では、液体や湿気に注意しなければなりません。もし万が一液体をこぼした場合は、放置せずにすぐに対処する必要があります。
怪我の原因になる
傷や汚れが畳の表面上にはなかったとしても、長期間畳を使用していると毛羽立ちや、ささくれが発生してしまい、ケガの原因になります。細かいささくれが体に刺さる可能性もあるので、こまめなメンテナンスが必要です。
畳の傷やへこみ防止におすすめのグッズ

天然のい草で作られた畳はクッション性があり、衝撃を吸収します。その一方で、重い家具をのせると傷やへこみができやすいので、キレイな畳を維持するための対策が欠かせません。
畳の傷やへこみ防止には、市販の防止グッズを活用しましょう。身近なホームセンターや家具店で購入できます。いくつか種類があるので、部屋のインテリアにあわせて使いやすいものを選んでください。
い草座卓敷き
い草座卓敷きは小さな畳状の敷物で、テーブルや椅子の脚の下に敷いて使います。家具の重みを面で分散させることにより、傷やへこみを防げます。
い草座卓敷きは畳と同じ素材を使っていて、見た目に統一感があるのが魅力です。和室のインテリアによく馴染み、違和感なく使えるでしょう。
い草座卓敷きには、丸形と四角形があります。部屋のアクセントになるカラフルに染色した商品もあるので、部屋の雰囲気に合うものを選んでみてください。
ジョイントマット
ジョイントマットはEVA樹脂製で、数枚を組み合わせて必要な面積だけをカバーできるアイテムです。軽くてクッション性があるので、お子様やペットのいるご家庭におすすめです。
ジョイントマットは色柄が豊富で、家具の下に敷いて使うと和室の雰囲気をガラリと変えられます。一方で、通気性が悪く畳との間にホコリや湿気が溜まりやすいのでこまめな掃除が必要です。
コルクマット
コルクマットはクッション性とともに、断熱性と防音性にも優れているのが特徴です。またサイズ展開が豊富で、家具の脚がのる程度の小さなサイズから部屋全体を覆う大きなものまで揃っています。
コルクは畳と同じ天然素材で和室に馴染みやすく、家具の下に敷いて使うとモダンな印象にまとめられるでしょう。ただし、室内全体を覆うと畳の通気性が悪くなるため、最小限のスペースで使用することをおすすめします。
防振マット・多目的EVAクッション
小さなお子様がいるご家庭には、防振マットや多目的EVAクッションもおすすめです。どちらも安価で100円ショップでも購入できます。うっかりお茶やジュースをこぼして汚れた場合でも水洗いできるのが特徴です。
防振マットや多目的EVAクッションは、白・黒・透明などのカラーバリエーションがあり、形や色、厚み、サイズもさまざまです。室内で目立ちにくいものを選べば、部屋の雰囲気を変えることなく畳を保護できます。
チェアマット
畳の上でキャスター付きの椅子を使う場合は、チェアマットを活用しましょう。チェアマットは、床材の傷を防ぐ椅子専用のマットです。サイズが大きく、キャスターの可動範囲全体をカバーできます。
チェアマットは大きく分けて、透明で硬さのあるクリアタイプと、ポリエステルなどのやわらかい素材を使ったカーペットタイプの2種類があります。クリアタイプはポリカーボネート製で、畳との間に湿気がこもりやすいため、使い方に注意が必要です。
ウッドカーペット
ウッドカーペットは、畳全体に敷くので畳を隠すことになります。簡単にフローリングのような状態にできるので、部屋の雰囲気を変えたい人にもおすすめです。
ウッドカーペットの裏地には、コットン布や不織布が貼られているため、畳を傷つけることはありません。また、敷いたりはがしたりするだけなので、原状回復も簡単なのがメリットです。また、種類が豊富でインテリアを楽しめ、コストも抑えられます。
一方で、敷き詰めようと思ったら、畳の大きさに合わせてカーペットをカットしなければならないので、手間がかかるのがデメリットです。また、畳の上に敷くので畳とカーペットの間に湿気が発生してカビが生えるおそれもあるので注意しましょう。
ラグ
ラグも、畳へのダメージが軽減されるだけでなく、インテリアとして楽しめる点でおすすめです。しかも、ラグはデザインやサイズの展開が充実しており、大掛かりなリフォームを行わなくても簡単に部屋の印象を変えられます。
畳に敷くラグは、通気性が良いものを選ぶのが鉄則です。通気性が悪いものだと、ラグと畳の表面の間にカビが生える可能性もあります。なるべく通気性が良いものを選び、カビを防止してください。
また、新品の畳にラグを敷くのは避けましょう。新品の畳はまだ水分を含んでいるので、その時点でラグを敷くとカビが生えやすくなってしまいます。青みが抜けてから敷くのが正解です。
ほかにも、敷いたあとはたまにラグをめくって畳に風をとおしましょう。適度に部屋の窓を開けて換気をするだけでもカビの発生を防ぐことができます。
畳の傷防止でマットを敷くときの注意点

畳の傷を防ぐためには、和室にカーペットやマットを敷くのも効果的です。カーペットやマットを敷く場合は、次の点に注意してみてください。
防湿防虫シートを敷く
カーペットやマットを畳の上に敷くと、湿気やホコリがこもりやすくなります。カーペットと畳の間に防湿防虫シートを挟むと、ダニやカビの繁殖を抑えられるでしょう。
カビやダニは、湿度が高いところや、食べかす・ホコリ・髪の毛が落ちているところを好みます。そのため、カーペットやマットは敷きっぱなしにせず、こまめに外して掃除機をかけることも大切です。掃除の際の手間を減らしたい方は、必要な部分だけを覆う小さめサイズのカーペットを使用することをおすすめします。
湿気対策を万全にする
天然のい草で作られている畳は、湿気に弱い床材です。畳には調湿作用がありますが、カーペットやマットで覆ってしまうと調湿作用がうまく働かず、湿気が溜まりやすくなります。日頃から湿気対策を欠かさないようにすることが大切です。
湿度が上がる梅雨時や暖房を使用する機会の多い冬場は、こまめに換気することが必要です。窓を対角線上に2ヶ所以上開けると風の流れが生まれ、効率良く換気できます。除湿機やエアコンの除湿機能を活用するのも良い方法です。
また、天気の悪い日に室内干しをすると室内の湿度が上がります。畳が傷む原因になるので、洗濯物は和室以外の場所に干しましょう。
畳の状態を定期的にチェックする
定期的に畳の状態を確認することも大切です。畳全体をカーペットやマットで覆ってしまうと、畳の状態がわからなくなってしまいます。気づかないうちに、畳にカビやダニが発生しているかもしれません。
定期的にカーペットやマットを外してチェックを行い、さらに年1〜2回の頻度で大掃除しましょう。カーペットやマットを外して掃除機をかけたら、固く絞った雑巾で畳の表面を拭いて汚れを取り除きます。あとは風通しの良いところで、しっかり畳を乾かしてください。
ジョイント部分が少ないサイズを選ぶ
広い面積にジョイントマットを使う場合は、ジョイント部分ができるだけ少なくなるよう大判サイズを選ぶのがおすすめです。凸凹を感じにくくなり、歩いたときや寝転んだときの使用感が良くなります。
また、端の部分はジョイント部分のギザギザにホコリが溜まりやすいので注意してください。端専用のパーツも活用して、掃除の負担を減らしましょう。
畳に傷・ささくれ・へこみができたときの対処法

丁寧に使っていても、畳に傷やへこみができてしまうことがあります。傷が目立つ場合は張り替えが必要ではあるものの、軽度なものならご家庭でも対処可能です。
ここからは、ご家庭で畳にできた傷やへこみを修復する方法をみていきましょう。身近な道具で修復できることもあるので、ぜひ試してみてください。
畳に傷やささくれができたときの対処法
家具を移動する際に畳がこすれて、傷やささくれができるときがあります。放っておくと傷が広がってしまうため、早めに次の手順で補修しましょう。
【準備品】
・木工用ボンド
・水
・空の容器
・絵筆
【手順】
1.はじめに掃除機をかけ、雑巾で乾拭きをして畳の汚れを取り除く
2.空の容器に木工用ボンドと水を1:3程度の割合で入れて、補修剤を作る
3.補修剤を絵筆に取り、目に沿って撫でるように塗る
4.補修剤が乾いたら完了
応急処置として、畳の目に沿って消しゴムで軽くこする方法もあります。必要な物が家にない場合に、試してみてください。
【軽度】畳にへこみができたときの対処法
家具の重みで畳にへこみができたときは、熱を加えてい草をふっくらさせましょう。アイロンを使用するのが不安な場合は、ドライヤーでも代用できます。
【準備品】
・アイロン
・霧吹き
・濡れ雑巾
【手順】
1.畳がへこんだ部分に霧吹きで水をかける
2.へこんだ部分に固く絞った濡れ雑巾をあてる
3.雑巾の上から中温設定のアイロンをあてて加熱する
4.表面がふっくら戻ったら雑巾を外して乾燥させ、完全に乾いたら完了
畳を濡らすときは霧吹き2〜3プッシュ程度が適量です。へこみの範囲が広い場合は、多めに濡らしてください。高温のアイロンを長時間あてると変色する原因になりかねないので、様子をみながら作業することが大切です。
なお、畳のへこみの直し方については、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてみてください。
「「畳のへこみが気になる...」正しい直し方と予防策を紹介!」
【重度】畳にへこみができたときの対処法

ここまでの対処法を試しても直らない場合や重度のへこみがある場合は、畳の張り替えを検討することをおすすめします。
畳のメンテナンス方法には、新調・裏返し・表替えなどの方法があります。
新調は、畳を丸ごと新しいものに替えることです。畳の芯材が劣化したり傷んだりしている場合は、新しいものに替えたほうが良いでしょう。
裏返しと表替えは、これまで使っていた畳を再利用して張り替えることです。使い始めて2年~3年の畳なら、裏返しをおすすめします。4年~5年経っているのなら畳表(たたみおもて)や畳縁(たたみべり)を替えると良いでしょう。
畳の状態を見ながら、新調するか現在の畳を活かして張り替えるのかを検討しましょう。
まとめ
天然のい草で作られた畳は、デリケートな床材です。家具を置くだけでも傷やへこみができやすいため、市販の防止グッズを活用しながら、こまめなお手入れを心がけましょう。
畳についた小さな傷はご家庭でも対処できますが、ご家庭では対処できない傷が畳についてしまった場合は、プロへの依頼も前向きに検討してください。