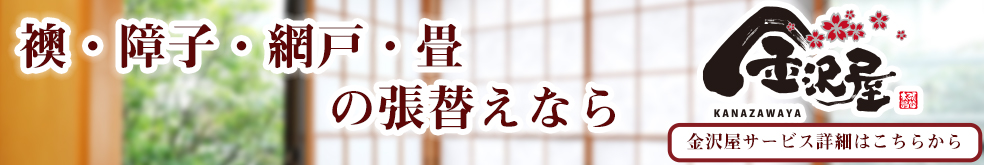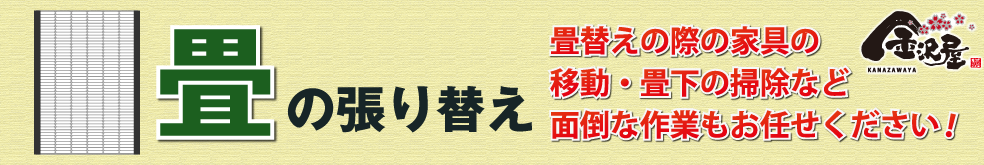目次
畳にカビが発生しやすいのはなぜ?

畳は、和室を代表するアイテムとして、日本で古くから愛されています。畳は、カーペットのように頻繁に取り換えることがないため、「難しいお手入れは不要」と思われがちですが、何もせずに放っておくとカビが生えてしまうことがあります。
ここでは、畳にカビが生えてしまう原因についてお伝えします。
カビが発生する原因
畳にカビが発生するのは、空気中に漂うカビの胞子が畳に付着するためです。ただし、付着するだけではカビは発生しません。
カビが発生するのは、「湿度」「温度」「養分」「空気(酸素)」「素材」の5つの要素が揃った場合です。
部屋の温度20度~30度、湿度75%以上という条件が長期間続くと、畳にカビが生えやすくなります。長雨が続く初夏の梅雨時期や秋雨の時期は、とくに注意してください。
また、冬場も油断はできません。和室で加湿器を使うご家庭は多いかと思いますが、冬に過剰に加湿器を使うとカビが発生するリスクが高まるため、使い方に注意が必要です。
昨今では住宅の気密性が高くなっており、高気密住宅の換気システムを止めたり十分に換気ができなかったりすると、湿気がこもってカビが発生するリスクが高まってしまうのです。そのため、1年を通してカビ対策が必要といえます。
カビのエサや栄養となる酸素や養分がカビ繁殖の要因となるのに加え、ホコリや水分を吸い込みやすい、い草の性質もカビの発生を助長します。そのため、近年ではカビが生えにくい和紙でできた畳の人気が高まっています。
カビが発生する場所
カビが発生する場所は、主に天然のい草が使われた畳表(たたみおもて)です。室内の湿度が高くなると、湿気を吸収し続けるため、カビが生えやすい環境となってしまうのです。
ちなみに、もっともカビに注意が必要なのは、新しい畳です。一方で敷いてから数年経過した古い畳は、い草がつぶれていて湿気を吸い込みにくくなり、カビが繁殖しにくいといわれています。
天然のい草は新鮮なものほど湿気をよく吸うため、新しい畳にはカビが発生しやすい傾向があります。湿度75%以上の天候が長く続くときは、畳をこまめにお手入れしてください。
カビが発生しやすいケース
湿度、温度、養分、空気(酸素)、素材の5つが揃ったときにカビは発生すると解説しましたが、具体的には以下のようなケースがあげられます。
・部屋の日当たりが悪い、風通しが悪い
・布団を敷いたままにしている
・カーペットを敷いたまま数年経っている
・部屋干ししている
このような状況が長期間続いたとき、畳にカビが生えやすい環境となります。自宅で当てはまるケースがあるときは、畳にカビが生えていないか確認してみましょう。
なかでも注意が必要なのは、布団の直敷きです。人は、眠っている間に一晩でコップ1杯、200ミリリットルほどの汗をかくといわれています。
人間の体から放出された寝汗は布団や畳が吸い取り、時間をかけて放出されていくものの、畳が吸い込める水分量には限界があります。布団を敷きっぱなしにしていると、畳の調湿能力が追いつきません。
水分を吸収し続けると、いずれ畳は飽和状態になります。そうなると、い草に湿気がこもって調湿作用が働かなくなり、カビが発生しやすくなるので、布団の敷きっぱなしには気をつけましょう。
畳に生えるカビの種類

畳に生えるカビは、種類によって色や人体に及ぼす影響が異なるため、見分け方を知っておくと安心です。ここからは、カビの見分け方を色別に紹介します。
緑のカビ
一般的には「青カビ」と呼ばれており、アオカビ・ペニシウム属という種類に含まれます。初期段階の軽度なカビですが、繁殖力が強いため、適した環境があればすぐに増えてしまいます。空気中を飛び回り、生息領域を拡大していくため、短時間で繁殖する可能性もあります。
青カビは特有のカビ臭をもっており、畳以外にパンや餅などの食品にも発生しやすいカビです。青カビがそのまま体内に入ると、体調を崩すおそれがあるため注意しましょう。
白いカビ
青カビ同様、カビとしては軽度の状態ですが、湿気が少ない場所でも繁殖できる強さをもっています。見た目が白くふわふわしており、畳以外に木材や壁、窓枠などにも発生しやすいカビです。空気中を舞うことも多く、掃除中に飛び散ってしまうこともあります。
白カビのなかには、麹カビ(コウジカビ・アルペルギルス)という種類もあり、こちらはやや乾燥した場所に増えやすい傾向があります。
黒いカビ
黒くなっているカビは、クロカビ・クラドスポリウムと呼ばれるカビです。掃除をしてもなかなか落ちない頑固なカビです。
エアコンの内部や浴室など、主に湿気が多い場所で発生します。水分を多く含んだ畳も、黒カビが発生しやすい条件が揃っています。
畳のカビをキレイに取り除く掃除方法

畳のカビは、部屋の環境や使い方によって生えてしまいます。ここでは、畳のカビをキレイに取り除くための掃除方法を、カビの状態別に紹介していきます。
薄くカビが生えている場合
畳に薄くカビが生えている状態のときは、アルコールやお酢で拭き取る方法がおすすめです。
【準備するもの】
・消毒用アルコール、またはお酢
・空のスプレーボトル
・ゴム手袋
・マスク
・雑巾
消毒用アルコールは、濃度が70%~80%のものか、無水エタノールと精製水を7:3の割合で混ぜたものを使用します。お酢を使用する際は、原液のまま使用しましょう。
空のスプレーボトルに、消毒用アルコールかお酢を入れて準備完了です。
【掃除方法】
1.部屋を換気する
2.消毒用アルコールまたはお酢をカビの生えた箇所にスプレーする
3.そのまま20分放置する
4.スプレーしたところを雑巾で拭き取る
5.仕上げに再度スプレーをして乾いた雑巾で拭き取る
6.部屋の換気をして畳を乾燥させる
手順1の「部屋の換気」は、掃除をはじめる前に行います。換気を行うことで、室内に浮遊しているカビの胞子を外に追い出す効果があります。天気が良いときは窓を開けたり換気扇を回したりしましょう。天気が悪いときはエアコンのドライ機能や除湿機を使うと効果的です。
手順5の「乾いた雑巾で拭き取る」際は、畳の目に沿って仕上げの拭き取りを行うと、目の奥まで消毒効果が行き渡ります。
黒カビが生えている場合
畳に黒カビが生えてしまったときはアルコールでの除去が難しいため、重曹を使用しましょう。
【準備するもの】
・重曹
・消毒用アルコール、またはお酢
・空のスプレーボトル
・使い古しの歯ブラシ
・ゴム手袋
・マスク
・雑巾
重曹はスーパーやドラッグストアで「掃除用の重曹」を購入できます。
消毒用アルコールは、薄くカビが生えたときの掃除方法と同じように、濃度が70%~80%ものか、無水エタノールと精製水を7:3の割合で混ぜたものを使用します。お酢を使用する際も同様に、原液のまま使用しましょう。
空のスプレーボトルに、消毒用アルコールかお酢を入れて準備完了です。
【掃除方法】
1.部屋を換気する
2.黒カビが生えた箇所に重曹を振りかける
3.黒カビを歯ブラシでかき出す
4.黒カビが取れるまで手順2と手順3を繰り返す
5.仕上げに消毒用アルコールかお酢をスプレーして乾いた雑巾で拭き取る
6.部屋の換気をして畳を乾燥させる
手順2の「黒カビが生えた箇所に重曹を振りかける」では、畳の変色を防ぐために黒カビが生えた箇所だけに重曹を振りかけます。また黒カビが生えたことで畳自体が黒ずんでいる場合、重曹を振りかけたあとに消毒用アルコールかお酢をスプレーしてください。
手順3の「黒カビを歯ブラシでかき出す」では、畳を痛めないよう、力加減に注意しながら行いましょう。
【注意点】畳のカビ掃除で気をつけたいこと

畳にカビが生えている場合、いくつかの注意点があります。普段何気なく行っている掃除方法が原因で、かえってカビを広げてしまうかもしれません。
ここからは、畳のカビを掃除するときの注意事項を解説します。
掃除機をかけない
畳にカビを見つけたとき、あわてて掃除機をかけるのはNGです。
掃除機でカビを吸い取ると、排気口からカビの細かい菌が排出されます。畳からカビを取り除く一方で、部屋中にカビをまき散らしてしまうのです。同じく、カビの生えた畳を叩いて払おうとするのも逆効果です。
掃除を始める前に、まず室内の窓を開けてください。換気をしながら掃除機を畳の目に沿うようにゆっくりとかけて、カビを吸い取りましょう。
水拭きしない
水拭きをすると、畳が水分を吸ってしまい、湿度が高まります。かえってカビの繁殖を招きやすいので、注意が必要です。
とはいえ、畳の掃除に水拭きがNGというわけではありません。畳は素肌に触れる機会が多いため、ベタベタする頑固な皮脂汚れやホコリを水拭きで取り除くと、すっきりします。水拭きしたあとは数時間換気して、畳の表面に水分が残らないようにしましょう。
乾拭きする
畳に薄くカビが生えた程度であれば、掃除機をかけたあとに軽く拭いても良いでしょう。ただし、乾いた雑巾でゴシゴシと強くこすると、畳の目の奥にカビが入り込むことがあります。
カビを除去しにくくなりやすいので、慎重に掃除してください。
カビキラーやキッチンハイターは使っていいの?
カビキラーには、消毒効果や漂白作用がありますが、畳のカビ掃除への使用は控えましょう。カビキラーを畳に使うと、畳の素材であるい草を傷めてしまうだけでなく、カビキラーの漂白作用で畳の表面に色ムラができてしまうのです。
キッチンハイターなどの液体状の塩素系漂白剤は、200倍以上に水で薄めてから、雑巾などに染み込ませてカビの部分を拭き取ります。薄めずにそのままカビを拭いてしまうと、畳の色素が抜けてしまうため、必ず薄めてから使用してください。水拭きをして漂白剤をしっかりと拭き取ったら、最後に畳を乾燥させましょう。
畳のカビを予防する5つのポイント

畳に生えたカビをキレイに取り除いたとしても、カビの生えやすい条件が揃うと、再度カビが生えてしまう可能性があります。
今後、畳にカビを生えさせないためには、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。ここでは、畳のカビを予防するポイントを5つ紹介していきます。
こまめに掃除する
ホコリや汚れはカビの栄養分になりやすいため、部屋をこまめに掃除することが大切です。定期的に掃除機をかけたりほうきで掃いたりして汚れをためないようにしましょう。
風通しを良くする
部屋に湿気をこもらせないように、天気の良い日は窓を開けて換気をしましょう。また換気扇やサーキュレーターで部屋の空気を循環させることも効果的です。
布団を敷きっぱなしにしない
布団を敷きっぱなしにすると、布団と畳の間の湿気が抜けにくいため、カビが生えやすくなります。布団をたたむことが難しい場合は、すのこを敷いて、直接畳の上に布団を敷かない方法もカビの予防につながります。
防湿シートの上に布団を置く
畳の上に布団やカーペットなどを敷く場合は、間に防湿シートを敷いておくのもカビ予防に効果的です。布団の下に溜まる寝汗を吸い取り、畳に湿気がこもるのを防ぐ効果が期待できます。
防湿シートには、ホウ酸塩を使用したものや炭のシートなど、いくつかの種類があります。なかには防虫効果が見込めるシートもあり、ダニの予防にも役立つでしょう。防湿シートの効果や持続時間、価格は商品ごとに異なるため、用途にあわせて選んでみてください。
畳をお酢で拭く
お酢の殺菌効果を利用してカビを予防する方法もあります。普段の掃除のあとに、お酢を含ませた布で畳の目に沿って拭くだけで予防効果を高められます。
カビが生えにくい畳の種類

畳の種類のなかには、カビが生えにくい素材のものもあり、種類や色のバリエーションも豊富です。ここからは、おすすめの畳を紹介します。
和紙の畳
和紙は、近年多く用いられるようになった畳素材です。耐水性や強度は、樹脂でコーティングすることでカバーされています。そのため、い草と比べてカビやダニが発生しにくくなっています。
い草に似た質感を出すために、和紙をこよりのように巻いてストロー状にしているのが特徴です。さまざまなカラーバリエーションが実現でき、部屋の雰囲気に合わせた畳が選べます。
樹脂の畳
樹脂の畳の主な素材はポリプロピレンであり、和紙と同じくストロー状にすることでい草に似た質感を楽しめます。樹脂は耐久性や耐水性も高く、飲みものをこぼしても浸透しにくいため、リビングや脱衣所などでの使用も可能です。
樹脂の畳は栄養分を含まないため、カビやダニの発生が抑えられ、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使えます。
スタイロ畳
スタイロ畳は、スタイロフォームという高性能の断熱材を使用した畳です。断熱性・保温性・防湿性に優れ、カビやダニの発生も防ぎます。従来の畳よりも軽量であり、掃除の際の移動も簡単です。
まとめ
畳に生えるカビは、体に悪影響を及ぼすため、こまめな掃除が必要です。加えて、あらかじめカビに強い畳に交換しておくことで、掃除の手間も軽減できます。
カビに強い畳への交換や、畳のカビに関するご相談は「金沢屋」にお任せください。金沢屋は襖・障子・網戸・畳の張り替え専門店として、全国各地で地元の職人が対応しています。
カビに畳が生えてしまってお困りの場合は、お客様の予算や要望に合わせて最適なプランを提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。